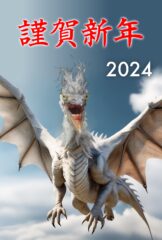7月14日に公開されたばかりの宮崎駿監督のジブリ作品、「君たちはどう生きるか」をさっそく観てきました。ジブリとしては事前情報を仕入れずに見て欲しいということなので、まだ観てない方はこの先は読まれないほうが良いかもしれません。もっとも、アオサギについての感想なので映画の内容にはほとんど触れていません。
というわけで、この映画、日本語のタイトルは上のとおりなのですが、英語版のタイトルは「The boy and the heron(少年とアオサギ)」と、これはもう他に想像しようがないほど単刀直入です。実際、少年とアオサギを中心に物語りが展開していきます。ただ、映画のポスターを見て勝手にイメージを膨らませると間違いなく裏切られます。私は多少なりともどこか神秘性があって先輩感のあるキャラクターを想像していたのですが、本編ではトリックスターのような役回りでしたね。まあでもあれだけデフォルメされていると、アオサギを見ているという意識はほとんどなく、自分のもっているイメージとのギャップに戸惑うことはありませんでした。顔は黒色の部分がアオサギというよりナンベイアオサギ(Cocoi Heron)のようでしたし、あの飛びながら魚を掬い取るというハサミアジサシ風の採餌方法はちょっとあり得ないかなと。まあアオサギのことですからひょっとするとやりかねないかもしれませんけど。逆に、アオサギらしさを感じたのは、中の人をゴクンと一呑みにしモノが喉を通っていくときの表現、それと何より主人公の部屋の窓から飛び立つ場面が印象的でした。飛び立つ前に脚を屈めてやや腰を落とすあのモーション、あっ、それちょっとやばいのではと思ったら案の定でした。あの予感の感じさせ方は実際にアオサギをよく観察していないと描けないものだと思います。
さて、問題はなぜアオサギなのかといういうことですね。あの鳥がアオサギでなければならい理由は映画では説明されてませんし、もしかしたらとくに理由はなく他の鳥や生きものでも良かったのかもしれません。ただ、古来、異世界を結ぶ役割には往々にして鳥が選ばれてきたことを思うと、ヘビやバッタやクジラを登場させるよりはアオサギのほうが理にかなっているのかなとは思います。けれども、私としてはそれが他の鳥でなくなぜアオサギなのかという部分にどうしても拘りたい。ひとつの推測としては、鷺を「路」+「鳥」とみなすことで、主人公に進むべき道を指し示す役として選ばれたのかなと。これについては、Twitterの@_a_n_o_a_nさんが私の昔の記事を発掘してくれたお陰で気付くことができました。ありがとうございます! その記事「鷺の漢字」では鷺の漢字の成り立ちについて白川静著「常用字解」を引用しています。
各はさい(注1)(神への祈りの文である祝詞を入れる器)を供えて祈り、神の降下を求めるのに応えて、天から神が下ることをいう。それに足を加えた路は、神の降る「みち」をいう。[説文]二下に「道なり」とある。異族の人の首を持ち、その呪力(呪いの力)で邪霊を払い清めたところを道といい、道路とは呪力によって祓い清められたみちをいう。
(注1):「さい」という字はアルファベットのUの真ん中にはみ出さないように横棒を引いた形。
道は道でもただの道ではなく神聖な意味が込められているのですね。このことは「古事記」に鷺が登場する場面からもはっきりうかがい知ることができます。アメノワカヒコという神様の葬儀の場面で、サギは箒をもち穢れを掃き清める役を受けもっているのです。そうであれば、映画のアオサギも異世界とつながる道を掃き清め、通れるよう道案内する役だったのかなとも思われてきます。もっとも、漢字で示される鷺という字はサギ類の総称であってアオサギとは限りません。古事記に現れる鷺は、その役回りを考えるとむしろ清廉潔白なイメージのあるシラサギが想定されていたと見るほうが自然でしょう。けれども、シラサギはキャラクターとしては融通が利かないというか、どうしても「白き衣の者に導かれ…」みたいなありきたりな展開になりがちです。そこへいくとアオサギは善にも悪にもなり得ますし、多面的な役を変幻自在にこなすことができます。トリックスターとしてはまさに打ってつけのキャラクターと言えるかもしれません。アオサギ、名役者としての本領発揮といったところでしょうか。